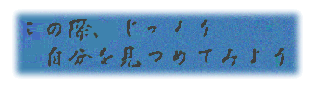 2004年 2004年 |
||
| 著者名 タイトル 出版社 値段 ページ数 |
心に残った言葉 | コメント |
上野千鶴子 信田さよ子 『結婚帝国 女の岐れ道』 講談社 \1700 289ページ 2004.5.20発行 |
上野節、快調。相変わらず痛快です。「だって、この人達は恵まれてるから」なんて言っちゃダメです。すっきりしましょう(^^ 色々語りたい部分はあるのだけど、今回、一番残ったのは、上野千鶴子さんのこの発言。 ・人間は社会的存在でなければならないということにも、わたしは深い疑問を持ってきました。なぜわたしが生きることに、他者の承認がいるのか?なぜわたしが他人の役に立つ存在でなければならないのか?そうでなくなったときのわたしは、生きる価値を失うのか? 「自分が存在するということに、他者の許可も承認もいらない」 昔、女に一方的に課せられていた縛めは今すべての人にのしかかってきていて(特に若者や子どもに)… 「強くあれ」「優れてあれ」「美しくあれ」「優しくあれ」「健康であれ」etc.確かに言葉としてはどこも悪くない… けれど、相矛盾するメッセージが人を追いつめる。「強く優れて美しく優しく」……そうでなければ、人は生きていく価値はないのか?社会の中で認めてはもらえないのか… 多分、この地点で停まってはいけないのだろう。そう、多分。自分の存在を許可し承認するのは他者や社会ではなく、自分自身でしかないのだろう。 三十代が一番しんどいだろうというのは想像が付きますね。だって、「成功できるか幸せになれるか、道は開いたぞ、後はすべて自己責任だぞ」てことにされてしまったんだもの。でも、道が出来たから幸せってもんじゃないのよ。自己責任て言葉は、成功は私だけのもの。失敗は、本人の責任というわけで。たださえ打ちひしがれている本人をむち打つものにしかならないのよね。当人だけのことならまだしも、夫とか子どもが絡むとね。子どもは親の思うとおりにはならないから、というか、ならなくて健全なんだけどね(三十代って、ちょうど小学生の親世代… ) |
|
今一生 『大人の知らない子どもたち』 学事出版 \1500 159ページ 2004.8.2発行 |
「ネット、ケータイ文化が子どもを変えた」というサブタイトルが示すように、昨今の子どもたちをめぐる事件・事象を解説し、著者である今氏の解説を加えたもの。この大部分が『月刊生徒指導』に連載されていたものだと思うと…まさしく隔世の感。よくこれだけ思い切った事を書けたなぁ。神戸・長崎・佐世保の事件を経て、やっと教育界は現実を見ようとしてるんだなぁ。すごくすごくよく分かるのですよ。そして、分かるのならば手を差し伸べるべきなんだろうとも思う。でも… 関わりきれない。関わりきれない大人の側の気持ちも分かる。一つは、“大人”の側にそれだけの余裕がない… もう一つは、同族嫌悪であり、近親憎悪なんだろうと思う。ここに現れている諸々の事象は、決して突然変異じゃない。以前から‘そこにあった’ものが、明確な形を取りだした事なんだろう。そういう意味では「知らない」ものではない。もし「私は知らない」というのなら、その人は幸せなんだろう。 ・呼びかければちゃんと返事をくれるひとがいるという安心 ・先生方はもちろん、親や教育に携わる大人たちが知るべきは、そもそも行政の方針には危険回避を優先的にふまえた教育プログラムなど無いのですから、学校にはケータイ&インターネットに対する満足な教育など出来ず、それらを利用したことで引き起こされるさまざまなトラブルの責任は負えない、ということです。 ・一生のうちで「いい子」でいなくても許される期間はずいぶんと限られているというのに、幼稚園/保育園を「お受験」のための予備校のように考えるのは、僕にはうすら寒い気がします。(中略)親からの視線が増えれば増えるほど子どもが息詰まる重苦しさを声を大にして訴えておきたいところです。 |
|
日野啓三 『書くことの秘儀』 集英社 \1700 186ページ 2003.1.30発行 |
日野啓三の遺作になってしまった本です。最後の作品が小説でなく、思索と想念(と言うしかないのですね。エッセーでも評論でもない)を述べた本というのも、この作家にはふさわしい……「なぜ小説を書きたがるのか。小説を書くことが、どうしてこれほど深く楽しいのか」
この問いに答えるに、個人にのみ還元するのでなく、現代科学の成果の力をも借りて理性的に追求しようとしたのが、すごく日野氏らしい。思えば『Living
Zero』でも、そうだった。まだ世界がバブルに踊っていた頃(1987)、なぜ文明が必要なのか、この‘繁栄’は何のためにあるのかを日野氏は突き詰めようとしていた。『都市の感触』(1988)や『都市という新しい自然』(1988)『どこでもないどこか』(1990)のシリーズで。 おこがましいを承知で言えば、日野啓三は私にとってすごく身近ですごく必要な人だという感覚がある。(この感じ、どこかで…と思って手繰ってみたら、穂村弘にも行き着きました。彼もまた言葉でもって、世界に対しようとした人だ)「人間は自分の夢によって現実をつくりだす」というのは、『夢の島』の一節だったか。 言葉でもって、世界と、そして自分と渡り合った人だった…… ・《人間》は実体ではない、繰り返し自己変革しながら新しいレベルの能力をつけ加えてゆくベクトル(方向性を持つ力)そのものだ、と考えると、そしてその力は宇宙的な起源を持つものかもしれないと想像していると、めまいがして気が遠くなりそうである。 ・「書く」ことによって「ほんとうのこと」が呼び出され呼び寄せられ、息を吹きかけられ血を注ぎ込まれ、影のように亡霊のように、近く遠く明るく暗く立ち現れるのであって、「書く」前にホントもウソもない。顔も水脈も陰影も混沌(カオス)さえもない。「書き方」だけが「ほんとうのこと」と「ほんとうに成り切れない」あるいは「ウソでさえもない」こととを分ける。 |
|
久世光彦 『わが心に歌えば』 主婦の友社 191P \1600 2003.7.10発行 |
「あのころ映画は美しい夢だった!―待望のシネマ・エッセイ。」という惹句からも分かるとおり、映画とその音楽から紡ぎ出された文…エッセイと言うよりももっと切ない。 いつの頃からか、演出家としての久世光彦は、遠い存在になっていったけれど、その分、文筆家としての久世光彦はすごく近しくなって、まるで背中のすぐ後ろに立ってるような気がすることがある。 この本も、その一つ。 それはもしかしたら、同じ地平を観るようになったからかもしれない…… 来し方と行く末…現在ばかりは見ていられなくなったから? ・少年の日に観た映画は、こうして今も私の中に生きている。(中略)それは、甘く感傷的な思い出ではない。あのころの映画たちが、いまの私を作った。つまり「地上より永遠に」は、いまの私なのだ。 ・「レベッカ」人の気持ちの翳りは、カラーでは表せないことが、ときにある。 ・ある一人の男の人生の半分は、二十歳過ぎまでの間に作られる。そのまた半分は〈少年時代〉と呼ばれる時期に作られてしまう。ずっと以前から、私はそう思っている。 9ページのフレーズにうわ〜(//▽///)「眠っているうちに見るのが夢の欠片ならば、覚めて想う夢は、永いときめきの物語である」 すっげーヨコシマ〜シマシマ〜さすが「悪魔のようなあいつ」を演出したお方♪ |
|